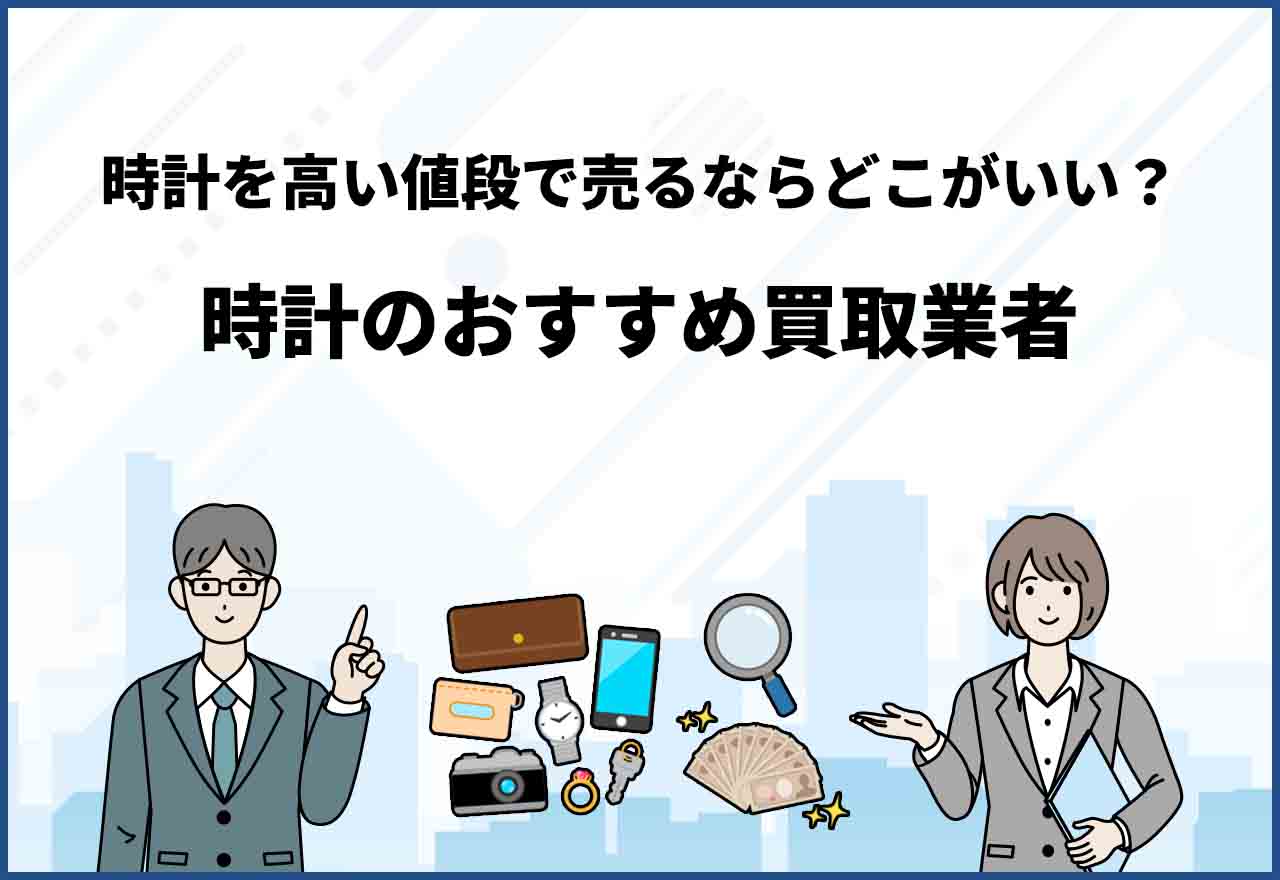『希少本星の信仰妙見信仰虚空蔵信仰北辰北斗星祭星供養星神信仰呪符天文道星宿曜道牛頭天王祭文蘇民将来呪符八坂神社祭神陰陽道密教蘇民将来』はセカイモンでfibrszksから出品され、64の入札を集めて02月27日 17時 53分に、37810円で落札されました。即決価格は37810円でした。決済方法はに対応。山梨県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。本の出品です。【即決】ご入札いただければすぐにお取引が成立します。
希少本 星の信仰 妙見・虚空蔵
佐野賢治 編渓水社 発行 北辰堂 発売約22.5x16x3.5cm511ページ函入 箔押布張り上製本
わが国には体系的星神信仰は存在しないこと、その欠如の理由などを考えることは、日本人の世界観、自然観の一端を明らかにする方法となる―日本における星に関する民俗の諸相を紹介し、そのような民俗の形成の歴史的背景を併せて考えられるように構成し、従来の難解な星に関する修法や経典の解説とは趣を変え、日本人にとっての星の意味、星神信仰の世界を総合的にとらえた論文集。 各論には膨大な数の参考文献、祭文などが付されており、明治維新の神仏分離・廃仏毀釈にともなってその存在が消えていった妙見信仰、牛頭天王などについても多数の文献資料から論考解説。 大変貴重な資料本です。
【目次】よりはじめに第一章 概論日本星神信仰史概論―妙見・虚空蔵信仰を中心にして 佐野賢治前言第一節 星をめぐる民俗さまざまな星の民俗 星祭り・星供-新潟県岩船郡朝日村大照寺の事例を中心に第二節 星神信仰の歴史星神信仰史の概観 古代律令国家と北辰祭 陰陽道と密教の星辰供 千葉氏、大内氏と妙見信仰第三節 虚空蔵寺院と妙見信仰虚空蔵信仰と妙見信仰 星辻神社と修験―秋田県男鹿半鳥を中心に第四節 星宮神社の成立-祭神分析を中心に栃木県の星宮神社 茨城・千葉・福島県その他の星宮神社 結語(図表…栃木県における星宮神社の分布図 星宮神社分布数 主祭神を経津主神、武甕槌神とする神社 主祭神を磐裂神、根裂神とする神社、千葉県における星宮神社と妙見神社 高知県下における星神社 ほか)第二章 星神信仰の歴史的展開〈天こう〉呪符の成立―日本古代における北辰・北斗信仰の受容過程をめぐって 増尾伸一郎はじめに 〈天こう〉呪符について 北辰・北斗信仰受容の端緒妙見信仰の伝播 宮廷儀式の変容と陰陽道祭の形成(静岡県浜松市伊場遺跡出土「百怪呪符」 ほか)日本古代における北辰崇拝について 廣畑輔雄斎王群行と北辰祭について 田中君於天文道と宿曜道 永井晋天文道を行った人々 鎌倉の天文道 鎌倉の宿曜道 金沢文庫の陰陽道勘文(明経道中原氏略系図 陰陽寮の位階構成 鎌倉時代中期安倍氏略系図 )疫病と神祇信仰の展開-牛頭天王と蘇民将来の子孫 今堀太逸はじめに 「蘇民符」の民俗と信仰 朝廷・幕府の疫病対策 鬼神と病①「疫鬼」と牛頭天王②密教と疫病 蘇民将来の呪符の成立①祇園の天神堂②天神と御霊会③「備後国疫隈国社」の縁起④牛頭天王と蘇民将来 牛頭天王社の展開①祇園社の勧請②牛頭天王社の祭文③若林天王社の「牛頭天王縁起」 おわりに日本に於ける疫神信仰の生成-蘇民将来と八坂神社の祭神研究 志賀剛はしがき 蘇民将来の研究①蘇民将来の武塔神および(八柱子)八王子の意味 ほか 八坂神社の祭神研究①八坂郷の景観②八坂神社の最新③八王子④牛頭天王⑤少将井(稲田姫命)⑥八坂神社成立の次第 むすび度会氏の星宿信仰-『高倉蔵等秘抄』をめぐって 山本ひろ子はじめに 「高庫蔵」のトポロジー 妙見星と北斗七星 星の象徴図像学へ中世の妙見信仰と祭祀組織-千葉氏の守護神と金剛授寺について 伊藤一男はじめに 千葉氏の妙見信仰 妙見社の神事 金剛授寺の性格 神領相論妙見信仰の千葉氏 土屋賢泰妙見について 妙見と千葉氏 まとめ大内氏の妙見信仰と興隆寺二月会 平瀬直樹はじめに 組織と景観 大内氏の妙見信仰と上宮 大内氏と二月会 むすびにかえて陰陽道祭についての一考察-若杉文書を中心として 遠藤克己はじめに 近世における陰陽道祭 若杉文書 陰陽道の祭文 安倍有春のこと 陰陽道祭文の分析 おわりに
第三章 星神信仰の民俗中国から日本ヘ―星をめぐる民間信仰 窪徳忠中国古代思想と星の信仰 日本での民間受容船と航海と信仰 国分直一星辰祭祀の残存とみられる地名について―特に日本の星神信仰の考察 倉田正邦はじめに 北辰・北斗信仰よりきた地名 七夕崇拝の祭祀による地名 赤星(明星)の信仰からきた地名 星宿の信仰からの地名 大将軍という星祭祀の地名 天一・太白の二星を信仰したと見られる地名 あとがき熊本の妙見信仰 安田宗生はじめに 文献に記載された妙見について 妙見信仰の様相 妙見の性格について 祭日と祭祀組織について 終わりに山口県から見た北辰信仰の諸相 金谷匡人はじめに 船を導く北辰 地におりた北辰 海に潜る北辰 おわりに~永遠の構造備後三原地方の妙見信仰 田地春江三原市東部 三原市西部 西部周辺地域 まとめ旗幟にみる呪符性 岡田保造緒言 乳の文様と呪符性 『甲陽軍鑑』に記された乳 乳と城 郭刻印 赤穂城の指南針 九字文と井桁文北斗七星と南斗六星の伝承 丸山順徳はじめに 子供の力命譚の分布 子供の寿命譚の特色 南北斗星と宇宙観 米寿祝いの民俗昔話「星女房」の行方―南島の伝承のなかに 福田晃日本の「天人女房」 星由来型「天人女房」の伝承態 「星女房」の伝承態 昔話「星女房」の伝承風土掲載論文初出一覧執筆者一覧
【巻頭カラー口絵写真】星曼荼羅(12世紀奈良県斑鳩町・法隆寺蔵、提供・小学館)七星剣(部分)(7世紀奈良県斑鳩町・法隆寺蔵、撮影・入江泰吉、提供・奈良市写真美術館)星供図(北斗図)(鎌倉~南北朝時代横浜市・称名寺所蔵、神奈川県立金沢文庫保管)奥羽列藩同盟軍旗(米沢市・宮坂考古館蔵、撮影・岡田保造)鬼瓦(京都市・妙心寺法堂鬼門部、撮影・岡田保造)蘇民将来(米沢市・笹野観音撮影・岡田保造)棟札(牛久市・観音寺撮影・佐野賢治)ほか
【はしがき】よりわが国には体系的星神信仰は存在しないこと、その欠如の理由などを考えることは、日本人の世界観、自然観の一端を明らかにする方法となる。また、このことは逆に、日本での星神信仰は、体系的な中国の星神信仰が宗教者の教導によって民間に沈下していく、一方的な過程ととらえてもよいことを示している。つまり、日本における星神信仰は、僧侶や貴族、武士といった特定階層の信仰としてまず受容され、一方で、民間での星に対する信仰の稀薄さから、様々な民俗におけるスターロア(星の民俗)は宗教者の関与を窺わせ、星神信仰を指標とすることにより、宗教者が民間に如何に接触したのかというプロセスを追求することができる。本書では、星に関する民俗の諸相を紹介し、そのような民俗の形成の歴史的背景を併せて考えられるように構成し、従来の難解な星に関する修法や経典の解説とは趣を変え、日本人にとっての星の意味、星神信仰の世界を総合的にとらえることを目的とする。また、無数の星を人間の観念と対応させ秩序づけることは、高度の精神活動であり、星が山岳、河川、草木などの自然環境に較べ普遍的であることから、他民族との比較の資料としても、興味深い示唆を与えてくれることになり、日本人の自然・世界観を探る糸口ともなることを期している。支配者にとっては治世の是非を問い、宗教者にとっては星供・星祭りとして、また、民間にあっては農事や漁業に結びついて展開してきたといえる。いずれにしろ、天の運行を人間社会に連動させるこの信仰は、地にあって竜脈の反映を家相・墓相に見る風水思想と合わさって、東アジアの自然と人文を統合する思想をその背後に窺わせてくれる。今後、天と地、星辰信仰、風水思想と合わせて論じる必要もある。概論では所収論文の位置づけもしながら、星神信仰の流れを述べたが、まさに大筋をしるしたにすぎない。快く論文の掲載に応じて頂いた諸執筆者に感謝の意を表すとともに、この一書を名の通りの北辰堂扱いで出版できることを喜びたい。
【各節の序文より一部紹介】日本星神信仰史概論———妙見・虚空蔵信仰を中心にして
佐野賢治前言星座は季節、日時による変動はあるものの、その存在は、不動、不変の感を人間に与えてきた。そのために、その調和を破る流れ星などに対してはさまざまな憶説が生まれた。また、無数の星を人間の観念と対応させ、秩序づけることは高度の精神活動であり、星が山、川、草、木などの自然環境に較べ、普遍的な存在であることから、民族による星辰観の相違などは比較民俗学上、興味深い示唆を与えてくれる。ここに、星神信仰研究の意義の一つがあるが、我が国ではこの星への信仰の稀薄さもあって、研究は立ち遅れていた。先学として野尻抱影の諸業績があり、民俗・歴史学方面では内田武志、金指正三、科学史の吉田光邦により体系的にまとめられるようになった。星神信仰研究の第一歩として、星座に対する科学的知識が要求され、さらに心意の反映した神話等の構造分析までその範囲は広い。ここでは虚空蔵信仰を中心に日本の星神信仰の素描を試みたい。
〈天こう〉呪符の成立―――日本古代における北辰・北斗信仰の受容過程をめぐって 増尾伸一郎全国各地から出土している木簡の内、呪語や符号あるいは神仏名などの記された呪符もしだいに数がふえつつある。これらの形状や記載内容は一様ではなく、いずれも何らかの宗教的な祭儀に関連したことが推測されるものの、年代や機能の明確な例はさほど多くない。その中には〈天〉という語句のあるものがいくつかみられるが、〈天〉は古来中国において北辰あるいは北斗、また十二月将の八月将を意味した。十二月将は日月の相会するところの十二神で、主に陰陽家によって使用される。〈天こう〉と北辰・北斗に関しては、種々の論議があるが、新城新蔵氏によれば、辰の字義は季節の早晩を示すために観測する標準のもの、即ち観象授時の対象の謂であり、具体的には、中国天文学の発達に伴って観象の内容も順次、参(オリオン)、大火(蝎座の第一星)、北斗、日月之交会点(十二辰)、日(太陽)と変遷をたどった。特に北斗は三~四〇〇〇年前には現在に較べて著しく北極点に近く終夜観測でき、北方の天空にみえる辰なるが故に北辰、または北方の究極にあるが故に北極とも称えた、とされる。近年、日本古代における道教の受容形態に関する問題が多くの関心を集めているが、本稿では、この〈天こう〉呪符に注目し、その成立と性格の検討を通じて、古代日本における北辰・北斗信仰の展開過程を跡付けることにより、道教受容史の一端を考察したいと思う。
日本古代における北辰崇拝について 廣畑輔雄奈良朝以前にわが国に見られる北辰崇拝の特徴は、それが中国より伝来したものであつて、天皇崇拝と深い関連を持つていると思われることである。このことについて若干の考察を試みたい。わが国最古の漢詩集『懐風藻』に、采女比良夫の「春日侍宴応詔」と題する次のような詩がある。論道与唐 … 北辰上この詩の最後の句の「北辰」の語は、天皇あるいは皇室を指し、「宜献南山寿、千秋衛北辰」の句は、これに対する忠誠の意を表明したものと見られるので、この詩は、天皇を尊崇して北辰に擬した当時の風潮を、端なくも表わしていることになる。わが国の天皇の称号が中国古代の天皇思想に依拠することは、既に津田左右吉に説があるが、天皇あるいは皇室を指…
斎王群行と北辰祭について 田中君於北辰とは「北極。謂之北辰。」とある如く「北極星」のことで、北極星を祀る祭りが北辰祭である。この信仰は、大陸との交渉により齎され、平安朝に入ってようやく盛んになった。この祭りは、中国に於いて漢代より、天子が春秋二季、東南郊に北辰を祀り、冬至の日の早旦に南郊に北辰を祀ったものが、わが国にも伝来し、平安中期頃に至って年中行事として定着したものである。この北辰祭も場合により、停止されることがあり、その一つが斎王群行の時である。これは『延喜斎宮式』勢江州忌条において、斎王群行の九月を"斎月”と定め、北辰に御燈を奉ることを禁じている。北辰の奉燈を禁止する理由は、斎王群行のためとだけある。そこでどのような関係により、更にはどのような経過をたどり禁止されるようになったものかを本稿で考察してみようと思う。
天文道と宿曜道 永井晋天空に輝く星を観て運勢を判断する占星術は、中世の日本でも行なわれました。中世日本の占星術は、天文道、宿曜道と呼ばれています。天文道と宿曜道をおおまかに分けると、中国の国家占星術を移入して日本風にアレンジした陰陽道の占星術が天文道、漢訳された占星術書を中国に渡った僧侶が持ち帰り密教の星宿信仰と密接な関係をもって貴族社会に広めた占星術が宿曜道ということができます。また、占いの対象についてみると、天文道が天皇の運命や戦争・災害等の国家レベルの事象を占って朝廷や幕府のような国家規模の権力機構に奉仕したのに対し、宿曜道はホロスコープを使って貴族や官人個人の生涯運や年々の運勢を占って貴族社会に受け入れられました。武家の政権として成立した鎌倉幕府でも、京都と鎌倉の間の交流の拡大によって将軍を取巻く儀礼・祭祀が公家風に整備された摂家将軍のおんみょうじ、将軍を呪術的に護る人々として僧侶・陰陽師の制度が整えられました。ここでは、鎌倉時代中期の朝廷幕府の陰陽師・宿曜師を中心に、天文道・宿曜道が公家社会・武家社会に与えた影響をみてゆきます。
疫病と神祇信仰の展開―――牛頭天王と蘇民将来の子孫 今堀太逸日本には病気の原因を、神とか魂(コン・タマシイ)の祟り(タタリ)とする観念が古代よりある。ことに流行病については異国から伝来したもの、異国の鬼神のしわざと考えられたりしていた。公家社会・武家社会における疫病の予防と対策においては、僧侶や陰陽師が活躍したが、その祭りや祈の実施には莫大な費用がかかり、地域社会において簡単に実施できるものではなかった。それでは、民間における疫病の予防と対策はどのようなものであったのだろうか。牛頭天王は、かつて祇園社の祭神であり、疫病の神として全国各地に勧請された。各地に伝えられている正月の「蘇民将来子孫家・門」「大福長者蘇民将来子孫人也」の呪符や夏越の祓えに使用される「茅の輪」は、牛頭天王信仰として説明され、年中行事として定着したものである。それは牛頭天王が疫病の根源であり、疫病をもたらす悪神(眷属)たちを統御し支配する神であることより可能となった信心であるといえよう。また、牛頭天王の霊験が本地仏とされた薬師如来や観音菩薩の利益、すなわち「仏法の利益」にほかならないことが強調されることによって展開した神祇信仰でもあった。以上のように、筆者は牛頭天王信仰や蘇民将来の呪符の成立についての見通しをたてていた。ところが、平成四年十一月、京都文化博物館で創建一千年を記念して開催された「壬生寺展」において、その「第一部壬生寺の歴史」の展示の第一番に、平安時代前期の長さ九・二センチ、幅一・五センチの木札が「蘇民将来札」(元興寺文化財研究所蔵)として展示されていた。その展示図録の解説によると、この木札は平成二年の元興寺文化財研究所による壬生寺境内の発掘調査で出土したものとのことであった。この調査で検出された遺構・遺物は、壬生寺関係と平安京関係のものとに分けられるが、この木札は平安時代前期の平安京朱雀大路東側溝から土器類や瓦類とともに出土したとのことである。また、その解説には「蘇民将来信仰は古代より現代まで受け継がれているが、古代の蘇民将来札そのものは例が少なく、この資料が年代の明らかな最古の例になる」との説明がなされていた。はたして、この壬生寺出土の木札は、本当に疫病の予防と対策に呪力のあった「蘇民将来札」なのだろうか。本稿では、まず奈良・平安時代における朝廷の疫病対策を検討したい。ついで鎌倉幕府の対策を窺うことにする。そして、それら朝廷・幕府の疫病対策をふまえて祇園牛頭天王信仰が成立し、牛頭天王と蘇民将来との約束により、その子孫が守護されるという信仰が全国各地に展開することになったという経過を明らかにしたい。
日本に於ける疫神信仰の生成――――蘇民将来と八坂神社の祭神研究 志賀剛天然痘の発生は古く崇神紀に見えるが、奈良時代の蘇民将来伝説には武塔神(須佐之雄神・八王子)の名が見える。平安時代になると、疫神関係の記事は八坂神社の記録にたくさん出てくる。私は先づ、蘇民将来の発祥地を、朝鮮人の帰化人聚落のあつた福山市に求め、疫隅国社は同市の王子神社で、式内深津郡須佐能袁能神社に当たることを確めた。次に、八坂神社の祭神の八王子は狛氏の八坂郷から、牛頭天王は秦氏の大政所(京都下京の地)から祇園に迎へたであらうと推定した。八坂神社に於いて注目すべきは、武塔神の代りに強力な疫神たる牛頭天王を迎へたことである。素戔嗚尊は、東山の天神からこの霊鬼的な牛頭天王と習合し、後に神祇に昇格して薬師と習合したのであつた。尊の神格の進展経過は、朝鮮の巫術的宗教を真の宗教たらしめた神道の優秀性を語るものであらう。或はまた、タイラーの精霊(八王子)→靈鬼(牛頭天王)→神祇(素戔鳴尊)の宗教進化の一典型を示唆するであらう。天然痘といつても今ではピンと来る人は少ないが、一九八○(昭和五十五)年五月に世界保健機関(WHO)が「天然痘根絶宣言」をする迄は、ペスト(黒死病)と同様に、天然痘は人類の脅威であつた。日本にても、それは例外ではなく、古代の文献にその惨状が伝へられ、全国の津々浦々に至るまで、農業神と合体した祇園社・御霊神社等のない所は稀な程である。しかし、今では、そその疫神社の方面は忘却されて、普通の氏神とか農業神として祀られてゐる。しかし、昔の人々が疫病によつて如何に苦しんだか、そこからどんな信仰が生れたかを顧みることは、宗教史上重要な意味があると思う。天然痘の流行と、その対策については平安時代にその史料が最も多いが、これについてはあらゆる史料を駆使して論述された久保田収博士の『八坂神社の研究』がある。また「蘇民将来」については、全国的調査をなされた井上頼寿氏の「蘇民将来」(郷土玩具研究一号)がある。私は右の二名著とは視点を異にし、疫病と共に疫神も朝鮮から渡来したが、帰化人聚落を含む文化地帯から、神名もその信仰も日本化していった過程を追求した。
度会氏の星宿信仰『高庫蔵等秘抄』をめぐって 山本ひろ子伊勢神宮外宮――。中世から近世を通して内宮をしのぐ勢力を誇ったその一大宗教拠点を管掌していたのが、外宮祠官・度会一族であった。天村雲命を遠祖とし、神武天皇の世に伊勢津彦を討伐し功を立てた天日別命の裔との伝承を持つ度会氏は、外宮・豊受皇太神宮の祭式一切をとりしきるのみならず、行忠、常昌、家行といった宗教思想家を生み出し、壮大な中世伊勢神道を展開した。密教、陰陽道、宿曜道などをも取り入れたその独自の宗教的展開のありようは、一族の同族祭祀である山宮祭にも窺うことができる。山宮祭は、内宮の荒木田氏も行なっていたもので、柳田国男の「山宮考」によって知られるように、一般的には先祖の霊を祀る儀礼と解釈されているが、度会氏のそれは単に祖霊祭祀にとどまらぬ複雑な要素を抱えこんでいた。そしてとりわけ濃厚にそれを彩っていたのが、北斗妙見大菩薩を中心とする星宿信仰であった。本稿で論じる『高庫蔵等秘抄』には、山宮祭の発祥として次の話が語られている。貞観元年、度会氏の遠祖・大内人高主の娘で大物忌の少女が御贄河(豊川)で水死した。遺体を探したが見つからず、代りに妙見星の童形の像を得たので、尾上の御陵の聖地に安置し、岡崎宮として祀った。その翌年から高主には三年続けて双子の男子が誕生した。その六男・春彦が、三十歳の時、妙見菩薩の霊託を受けて、氏人を率いて清浄の山谷で妙見菩薩や日光月光、孔雀王や八神を祀ったのが、山宮祭の始まりであるという。――この尾上の御陵は古くから度会一族の葬地があったらしく、度会二門のゆかりの常明寺も存在した。岡崎宮妙見堂には、長く妙見菩薩像が安置され(正安三年=一三〇一の年記のある像が現存し、現在読売ランドに祀られている)、古くから度会氏の女性たちの信仰を集め、江戸時代には一族の胞衣を埋納する風習があったという。さらに山宮祭で誦まれた祭文を覗くと、そこには「妙見大菩薩の御門人」である一禰宜が氏人らと「結縁同心」して、妙見大菩薩に「大御調」を供奉するために、「天八大神」「土公五帝」「行年神」などの座を用意し、幡や「五殻ノ粥」などの供物を献ずる神事であると述べられている。このように、度会氏はその始祖伝承から、北斗妙見への信仰を抱えこんでいたのであった。だが、その妙見信仰は、単に一族の始祖伝説の範囲にとどまるものではなく、外宮・高倉山や、神宮本殿、心の御柱をも含み込んだ、大きなコスモロジーの一端であった。本稿では、上記の『高庫蔵等秘抄』なる書に注目し、度会氏の星宿信仰の多様な姿を探っていきたい。
中世の妙見信仰と祭祀組織―千葉氏の守護神と金剛授寺について 伊藤一男上祭祀組織古代末期、平良文に始まる下総の千葉氏は、妙見信仰の伝承を秘めた武士団であった。鎌倉幕府の成立とともに、千葉氏は東国に確固たる地位を占め、多くの分族・支流が下総各地に割拠した。複雑に浸蝕・開析された下総台地の縁辺部には、中世の城館跡が点在するが、その多くは戦国時代、千葉氏系の武士団によって築かれたものである。城跡付近の要地には、必ず妙見社が勧請され、氏族結合の象徴とされてきた。近世以降、その氏子中には、千葉氏の支脈を称する旧家も多く、これらの家筋では月星・九曜などを家紋としており、さらに累代の刀剣・具足、伝来の文書を保管している例も数多い。古来、千葉氏が信仰を捧げてきた「妙見菩薩」は、北極星・北斗七星を神格化したものとされ、国土を守護し災厄を除く現世利益の神(仏)であると伝えられる。また、千葉氏の紋章にも星が用いられ、惣領家(嫡家)は「月星」、一門(庶家)は「諸星」を使用している。これも妙見信仰に由来するもので、まさに千葉氏一門は「星の集団」であった。
妙見信仰の千葉氏 土屋賢泰妙見の信仰にかんする資料と実証的な知識をあつめて整理し組織だててみたいと平素より思ってきた。さいわいなことに、千葉氏は妙見の信仰の伝承と史実をもつ武士団であった。妙見の信仰の流れをたどってみながら、古代千葉氏を中心に、この信仰の意味と役割を明らかにしようとするものである。
大内氏の妙見信仰と興隆寺二月会 平瀬直樹大内氏は、その勢力範囲の国々にある多くの寺社に対し、所領安堵などによって、その宗教活動を保護した。しかし、このような行為を、単に、大内氏の信心深さ、あるいは守旧的な性格の表れとして見るのではなく、その中に、領国支配政策の一環として、積極的に寺社を利用した側面を見出すことができないであろうか。すなわち、領国内の寺社が行う宗教活動には、大内氏への奉仕――いわば宗教による忠節――という側面があるのではないだろうか。そして、雑多に見えるそれら寺社の宗教活動も、大内氏を中心に据えて見ると、それぞれ特定の役割を持って――いわば宗教的な役割分担を形成して――行う奉仕であったと言えるのではないだろうか。本稿では右のような問題を検討するため、先ずは、その基礎的作業として、大内氏と個別の寺社との関係を考察したい。その第一歩として、大内氏と最も関係が深いと考えられる氷上山興隆寺を取り上げる。この寺に着目したのは、周防国吉敷郡大内郷という、大内氏のかつての本拠地に位置したうえに、その氏寺であったことによる。ここには、多数の中世文書が伝来しており、これらは、大内氏関係としては、最もよくまとまった文書群と言うことができる。そこで、この文書群を主たる史料として、大内氏が、この寺に何を求め、そして、その宗教活動が、同氏にとっていかなる意味を持ったのかということを考察してみたい。
陰陽道祭についての一考察――若杉文書を中心として 遠藤克己陰陽道は、わが国の上代から近世に至るまで、わが国の思想・民俗・文学など、広範囲にわたり、わが国の文化・社会の中にあって大きなウエイトをもってきたのであり、延いては、現代社会においても、その息吹が窺われるのである。陰陽道祭については、小坂真二氏「禊祓儀礼と陰陽道」「怪異祓と百怪祭」岡田荘司氏「陰陽道祭祀の成立と展開」など貴重な論究があるが、拙著『近世陰陽道史の研究』に於ても、若干、陰陽道祭に触れておいた。三万六千神祭を始めとして、天地災変祭・陰陽祭・鎮火祭・荒神祭・本命祭・地鎮祭・安鎮祭・鎮宅霊符神等、日次記にあらわれた江戸期の陰陽道祭について述べたが、就中、泰山府君祭、天曹地府祭は、陰陽道としての双璧といってよいであろう。
中国から日本へ――――星をめぐる民間信仰中国古代思想と星の信仰 窪徳忠いまから考えてみると、漢文を読むことのできた人たちは、江戸時代には大へんな学者、またはインテリだったにちがいない。かれらは漢文が読めたばかりに、とくに中国を先進国としてあがめ、その文化にあこがれをもっていたように思われる。かれらのあいだに、ともすると、日本の信仰や習俗、年中行事などの由来や源流を、中国に求めようとする傾向のつよかったのも、そのあらわれのひとつだったのではなかろうか。江戸中期の国学者蔀遊燕も、そういった傾向をもつひとりだったといってよかろう。
船と航海と信仰 北斗七星と船霊信仰 国分直一船と航海をめぐって、かねがね関心をもってきたものであるから、松本信広先生の追悼論文集『稲・舟・祭』(六興出版、一九八二年)に、「東シナ海の船と航海をめぐる問題」と題する小考を書かせていただいた。しかし執筆して一年もたたない間に、松本先生にささげた論考では解明が不十分であったり、まったく手にもつけることのできなかった問題にもやや近づきうるようになった。一つは華南系と想定してきた弥生時代のゴンドラ型船をめぐる新しい発見があったこと、第二は船霊信仰におけるサイコロの意味がとけてきたことによってである。松本先生にささげた論考において、まったく手もつけることができなかったと述べたのは、後者の船霊信仰である。以上の二つの問題をめぐって、自分ではやや展開をみせたと考えている考説を覚え書としてかかげ、松本信広先生の霊にささげたい。
星辰祭祀の残存とみられる地名について――特に日本の星神信仰の考察 倉田正邦わが国の信仰史の上で、もっとも明らかにされている一つに、大陸文化の影響を受けた「星神」の信仰が根強くあった。その一つの星神の信仰によって、伝承過程をみるとき、文化が宗教と結びついて発達し、更にそれと相結んで、信仰の対象的なる場所が地名の上に付けられている。日本に於ける星辰の信仰は、上代の時に輸入せられたものであることは、論をまたないにしても、多くの星を眺めている間に、それぞれの地方によってその方言なり、表現方法が変っている。原始民族は、農耕生活によって季節を送り、その季節の変化によって時刻を知り、祭祀を行って来た民族であるが、その暗黒なる時代に、何をみつめるのであったか。それは遊星する数々の星の移動と、星による観測であったとおもわれる。どこの民族でも、古代人は人の吉凶は星のまわり合せでくるものと信じ、そこで選日、星供養ということを大切な行事としているのであって、正月に行う『お待”という行事は、もとは星供養で、「よい日のくるのを待つ」という平安時代の真言修験者が行っていたものである。ことに日本のような島国の民族にあっては、航海民族の間には特に天文暦の発達が大きかったであろうし、星辰の力が…
熊本の妙見信仰 安田宗生よく知られているように妙見信仰は星信仰の一つである。日本における妙見信仰については修験道において受容せられ、その後日蓮宗においても信仰の対象となり、全国的な展開が見られるようになったとされる。しかし、九州における妙見信仰がいかなるものであるかについての調査研究は十分行われてきたとはいえない。熊本においても信仰の実態について民俗学的な追究はほとんどなされていない。熊本における妙見信仰については、八代の妙見について研究がある程度といっても過言ではない。八代妙見については、多くの文献史料があり、中国伝来説によれば妙見は八代郡土北郷白木八千把村竹原の津、百済説では八代郡不知火崎に到着したとされている。そこから下益城郡豊野村に一時期鎮座した後八代妙見宮に移ったとされている(文献については『肥後国誌』『妙見社伝旧記』等がある)。この八代妙見の信仰は亀を神の眷属として、これを粗末にしたり、食べることを禁止したりしている。八代神社の祭礼は十一月十八日の大祭が有名である。この祭りには亀蛇が登場する。亀蛇が登場する祭りは小川町にも見られるが、それ以外の地域には認められない。神体を見ると、亀蛇に乗る神像は八代郡や球磨郡に顕著である。熊本の妙見と言えば、この八代妙見に代表されるように思われているが、八代妙見社との関係を説かない妙見信仰が、熊本市とその周辺部を始めとして玉名、鹿本、上下益城、阿蘇、及び球磨の各郡に広範に存在している(もっとも、八代との関係があると思われる事例が北部地域の一部にある)。このような広がりをもつ妙見信仰について見てみると、一つの…
山口県から見た北辰信仰の諸相 金谷匡人人知の淵源は観察であり、人はその観察知識のうえに立ってその現象の背後にある目に見えない力を把握しようとつとめる。晴れた夜空において自ら動じず、諸々の星を周囲に配した北辰(北極星)を古の人々はどのように観察したであろうか。あるいは陰陽家において特徴的な反閉という歩き方(禹歩)は、北斗七星を地上に投影させてそれを踏み歩く作法であるともいう。神楽や太極拳において目にすることの多いこの歩き方の中に、人々はどのような意味を付与しているのだろうか。もとよりこのような小論ではその大きな宇宙に踏み込んでいくことはできないが、県下に残された記録類をたよりに、北辰に対する人々の思いに少しでも触れてみたいと思う。ただここで注意したいのは、一概に星に関する信仰といっても、それはいくつかの層をなしているということである。つまり、星そのものに対する人々の思いなのか、星の観察から生まれた宇宙観(宗教観)に対する人々の宗教的な思いなのか、あるいはそれを解釈することによって生み出された神仙世界に対する人々の憧れなのかといった問題である。人と宇宙という、限りなく遠くて近い問題であるがゆえに、個人の不老長生から帝王学まで、北辰のあらわれ方は様々であるが、この小論ではそのようなことを念頭におきつつ、その本質にちかづいてみたい。
備後三原地方の妙見信仰 田地春江妙見をまつるやしろは、記録でみる限り広島県内に於てさして数の多いものではない。しかし実地に当ってはかなりの数の妙見小祠又は妙見信仰集団が分布している所があり、式年には特殊な神楽をあげるしきたりが続いていた。今日まで広島県東南部を聞き歩きした所では、その信仰の分布は三原市周辺部に密で、遠ざかるに従ってうすくなっている。ここに報告するのは三原市を中心とした地域での妙見信仰の実態である。第一図は、藩政期の記録による妙見祠の分布図で、文政八年(一八二五)の『芸藩通志』を主体とし、『西備名区』(一八〇四)、『福山志料』(一八〇九)、『備陽六郡志外篇』(一七七六)を以て東部を補い、更に不足な部分を、甲奴郡上下町桑田家に残された安政三年(一八五六)の明細帳を以て出来るだけ埋めた。この明細帳は、広島県史編纂室の御好意により閲覧を許されたものである。これらの記録は小祠についてはかなりの省略があるので、特に妙見の様に一部の信仰と思われがちなものについては不充分であると思うが、一つの目安にはなるであろう。妙見には明見、妙剣、妙現など様々なあて字があるが、本稿では記録の引用以外は妙見に統一した。
旗幟にみる呪符性 岡田保造陰陽道の盛行や密教の伝来、それに修験道の中興と呪術性に富む信仰が貴族をはじめ広くに浸透した平安時代につづき、戦いに生命を賭す武士の世もさらに除災招福を祈って呪術的信仰に走り、信仰の具現として築城をはじめ生活の多くの面に呪符を用いるようになった。筆者は近世城郭の石垣刻印に呪符を求める過程で多彩な呪符の使用例を知ったが、本論では旗幟の乳(縁に、竿などを通すために付けた小さな輪)と築城作法に用いられた安倍晴明判文や九字文など呪符の種類と、呪符となる文様の持つ呪符的意味を探った。特に旗幟の乳に用いられる呪符的文様は石器時代以来後世の服飾や馬具にまで用いられており、その心は現代の占いブームにまでつながるものである。安倍晴明判文の呪符的要素の考察を端緒とし、近世城郭の石垣に彫られた各種の刻印について、その呪符性の有無を求めて寺社の石垣・石敷・鬼瓦など呪符となる文様の確認を進めているが、その過程で見出した旗幟の乳に刺繍された文様の呪符性について明らかにしたい。
北斗七星と南斗六星の伝承 丸山顯德『日本昔話集成』一五二番の「子供の寿命」は、紀元四世紀の半ば頃に、中国の晋の干宝が編んだ『捜神記』に収められている。新しい時代では、明の長編歴史小説『三国史演義』に収められており、もともと中国に発生した話のようである。この話型は、中国、韓国、北朝鮮、及び日本に分布しているが、特に沖縄地方にこの話型が濃く分布していることが特徴的なことである。このことが明らかになったのは、昭和四十八年八月に始まる、立命館大学、大谷女子大学、沖縄国際大学の三大学による沖縄口承文芸調査団、及び沖縄国際大学口承文芸研究会を軸にして発展した沖縄民話の会と、奄美沖縄民間文芸研究会の採訪の成果によるものである。昭和二十年代の終わりから三十年代にかけて編集された『日本昔話集成』の中で、「子供の寿命」のモチーフの認定は、まだ十分熟したものではないように思われる。それは沖縄の資料が十分でなく、主として鹿児島県の資料によったものであったからである。昭和五十二年十二月に刊行された『日本昔話事典』(弘文堂)にも、どういうわけかこの話型が事典の項目から漏れている。
ほか
〈執筆者一覧〉増尾伸一郎 東京成徳大学助教授廣畑輔雄 元高知女子大学講師田中君於 石清水八幡宮研究所研究員永井晋 神奈川県立金沢文庫学芸員今堀太逸 佛教大学助教授志賀剛 逝去 文学博士山本ひろ子 フェリス女学院・埼玉大学・明治学院大学非常勤講師伊藤一男 九十九里総合文化研究所研究員土屋賢泰 日蓮宗来伝寺住職平瀬直樹 山口県文書館専門研究員遠藤克己 文学博士 日本大学史学会参与窪徳忠 東京大学名誉教授国分直一 梅光女学院大学地域文化研究所教授倉田正邦 元愛泉短期大学教授安田宗生 熊本人学助教授金谷匡大 山口県史編さん室専門研究員田地春江 日本民俗学会会貝岡田保造 大阪成蹊女子短期大学教授丸山顕徳 花園大学教授福田晃 立命館大学教授
〔編者略歴〕佐野賢治1950年 静岡県生れ1974年 東京教育大学文学部史学科卒業1979年 筑波大学大学院歴史・人類学研究科単位取得退学現 在 愛知大学講師・助教授を経て,筑波大学歴史・人類学系助教授編著者『虚空蔵信仰』(1991,雄山閣出版)主論文「祖霊化過程と仏教民俗」(『日本仏教』42)「十三塚と十三仏」(『十三塚』平凡社)ほか
★状態★1994年のとても古い本です。函の外観は通常保管による経年並ヤケしみスレ程度、箔押布張上製本外観は経年の割に比較的良好。裏見開きに小ラベル跡ありますが、本文目立った書込み・線引無し、問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)
<絶版・入手困難本>オークションにも滅多に出ない、たいへんに貴重な一冊です。古本・中古品にご理解のある方、この機会にぜひ宜しくお願いいたします。
★お取引について★■商品が到着しましたら、必ず「受取連絡」のお手続きをお願い申し上げます。■中古品です。それなりの使用感がございます。モニタのバックライトの作用により、写真画像は実際よりきれいに見えがちです。■絶版・廃盤、一般の書店で販売されない限定販売、書店や出版社で在庫切れである、またはその他の理由により、定価に関係なく相場に合わせて高額となる場合があります。■「かんたん決済支払明細」の画面を保存・印刷することで領収書に代えさせて頂きます。■PCよりの出品です。携帯フリマサイトのようにすぐにご返信はできかねます。■かんたん決済支払期限が切れた場合、連絡が取れない場合、落札者都合にてキャンセルいたします。■土・日・祝日は、取引ナビでの応答・発送をお休みしております。他に連絡・発送のできない日は自己紹介欄に記載しております。■万一、商品やお取引に問題があった場合は、いきなり評価ではなく、取引ナビにてご連絡ください。誠実に対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。
■上記の点をご了承頂ける方のみ、ご入札くださいますようお願い申し上げます。
★商品の状態について★Yahoo!オークションが定める基準をもとに、出品者の主観により判断しています。以下は公式ページより選択の目安より転載します。
新品、未使用…未開封の新品、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品未使用に近い…中古ではあるが数回しか使用しておらず、傷や汚れがない目立った傷や汚れなし…中古品。よく見ないとわからないレベルの傷や汚れがあるやや傷や汚れあり…中古とわかるレベルの傷や汚れがある傷や汚れあり…中古品。ひとめでわかるレベルの大きな傷や汚れがある全体的に状態が悪い…中古品。大きな傷や汚れや、使用に支障が出るレベルで不具合がある。ジャンク品など。










セカイモン販売中の類似商品
-

ドストエフスキー : 総特集
¥ 20,320
-

【中古】 盆栽専科小品盆栽 (1979年)
¥ 23,190
-

【中古】 源氏物語考証稿
¥ 41,970
-
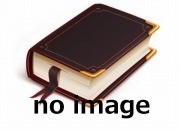
天台大師の研究 正続揃い 佐藤哲英
¥ 39,550
-

Domani 2007 12 春香
¥ 6,320
-
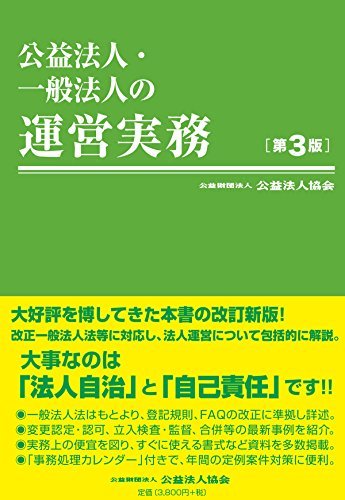
【中古】 公益法人・一般法人の運営実務 第3版
¥ 20,950
-

Domani 2011 10 知花くらら
¥ 6,080
-

Domani 2003 4 川原亜矢子
¥ 6,960
-

【定価28万6千円】『西鶴研究資料集成 昭和前期篇』全12巻揃補巻1●2010年~2011年発行●クレス出版●検)江戸文学国文学俳諧和書古書古文書
¥ 50,460
-

相川町年寄伊藤氏日記
¥ 39,000
-
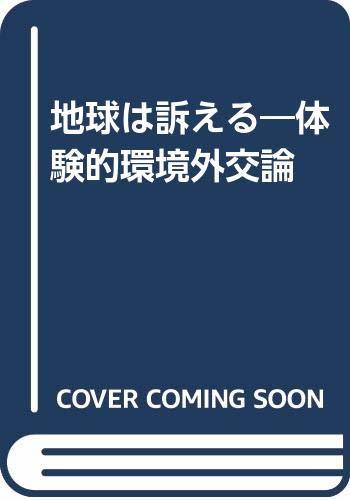
【中古】 地球は訴える 体験的環境外交論
¥ 20,290
-

【中古】 最低賃金・業種別・規模別 就業規則総覧
¥ 26,930
-

STORY 2011 7 富岡佳子
¥ 6,400
-

【中古】 Modernist Cuisine at Home 現代料理のすべて
¥ 29,230
-

平曲譜本の研究 (1981年)
¥ 40,520
-

本なんて!作家と本をめぐる52話
¥ 32,650
-

【中古】 未収金、未然防止・回収実践事例集 未収金、いかになくすか、回収するか!
¥ 37,410
-
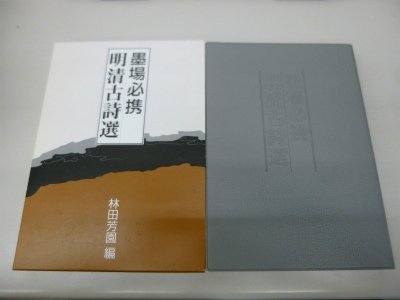
【中古】 墨場必携 明清古詩選
¥ 19,860
-

Ane Can 2010 4
¥ 7,360
-

ハイキュー 全45巻+33.5巻+関連書籍 全巻初版帯付き 特典数点
¥ 21,170
-
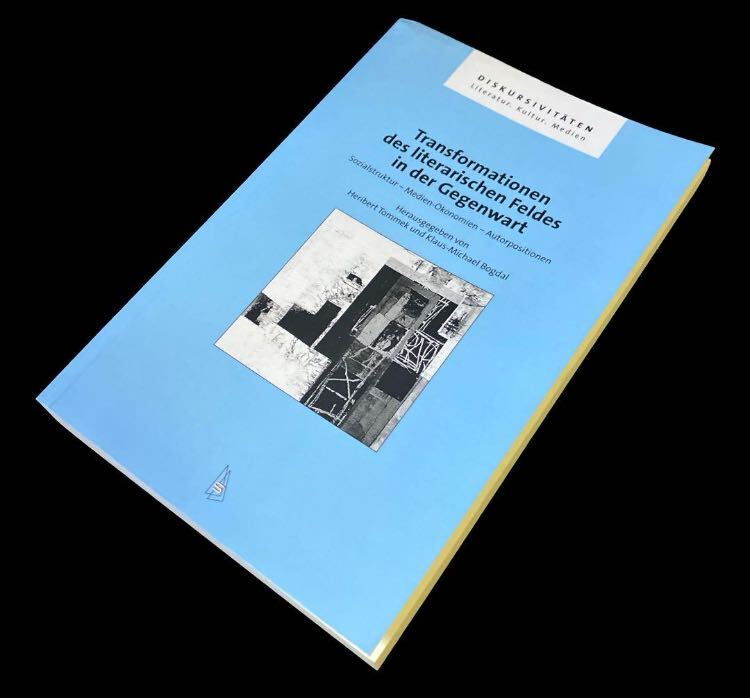
ドイツ語版 Transformationen des literarischen
¥ 22,880
-

■01)【同梱不可】【非売品】住岡夜晃全集/全12冊揃いセット/真宗光明団本部/仏教/宗教/C
¥ 47,400
-

ミセス 2012 12 草刈民代
¥ 6,750
-

25ans 2009 4 浦浜アリサ
¥ 6,800
-
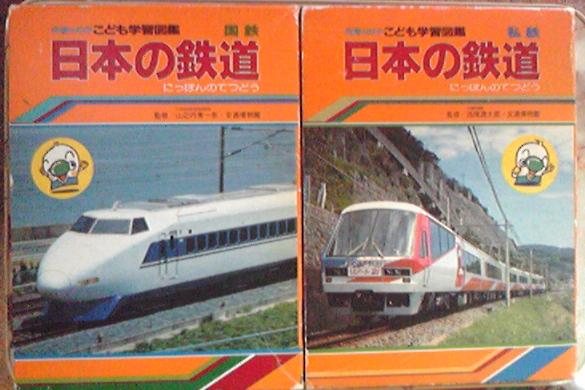
昭和60年 交通公社のこども学習図鑑「日本の鉄道 国鉄/私鉄」2冊
¥ 40,800
-

【中古】 名器と盛りつけ 懐石・辻留
¥ 31,970
-

【中古】 新国誠一works 1952 1977
¥ 24,060
- 落札情報
- 出品者情報
- 落札価格
- 37,810円
- 開始価格
- 37,810円
- 即決価格
- 37,810円
- 入札単位
- 100円
- 商品状態
- 未使用に近い
- 個数
- 1
- 開始日時
- 2024-12-23
- 終了日時
- 2025-04-10
- 自動延長
- なし
- 早期終了
- なし
- 入札者評価制限
- あり
- 入札者認証制限
- あり
支払い・配送方法
- 支払い方法
-
- 送料負担
- 落札者
- 発送元
- 山梨県
- 海外発送
- 対応しません
- 発送方法
- -
商品説明
こちらの商品をお気に入り登録しませんか?
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
会員登録で同じ商品を出品!
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
入札予約
最大10年分の相場を簡単検索!
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
- ※クレジットカードのみ初月無料の対象となります。
-
※登録月が無料となり、登録月の翌月より料金が発生します。
初月無料対象月内に利用再開を行った場合、初月無料の対象外となります。
期間おまとめ検索とは?
オークションで稼ぐための人気機能!

「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
最大10年分の相場を簡単検索!
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
- ※クレジットカードのみ初月無料の対象となります。
-
※登録月が無料となり、登録月の翌月より料金が発生します。
初月無料対象月内に利用再開を行った場合、初月無料の対象外となります。